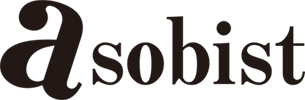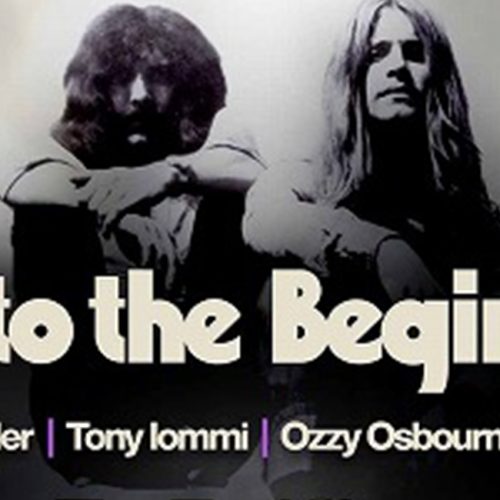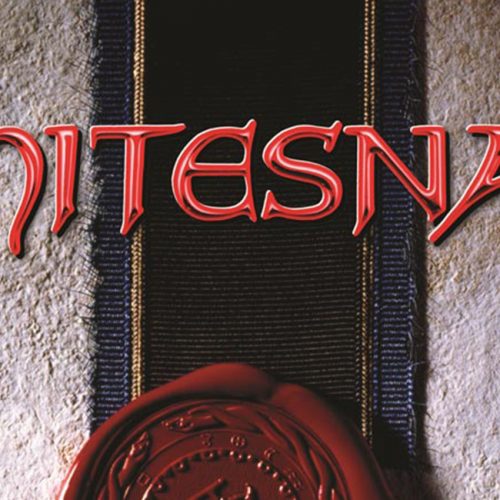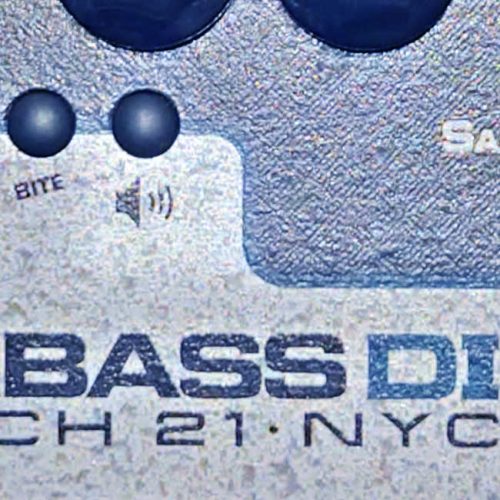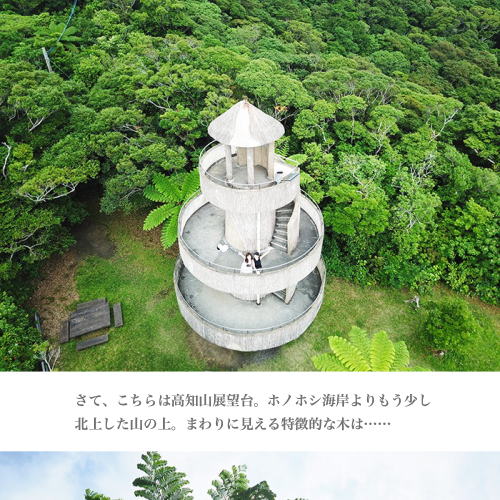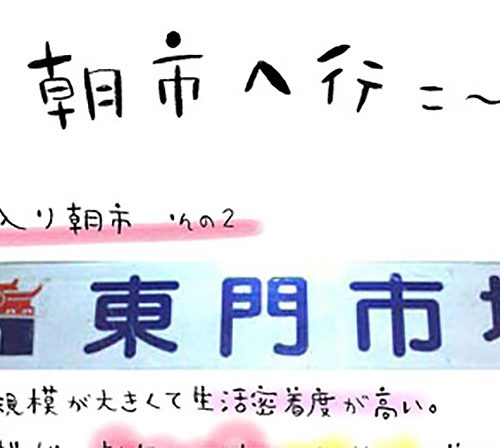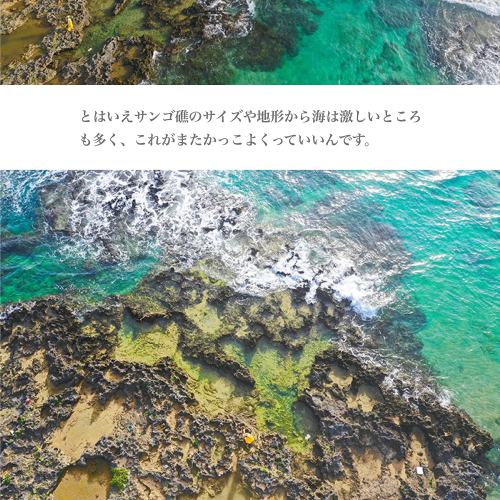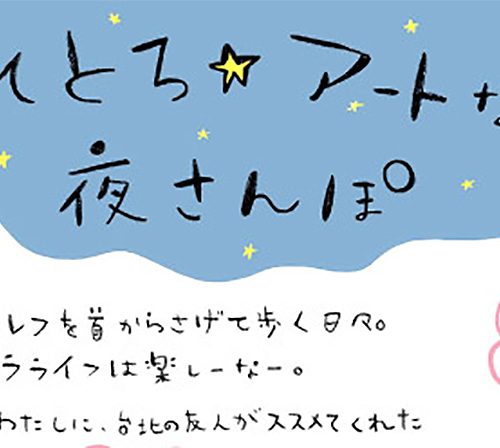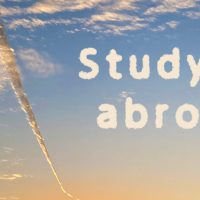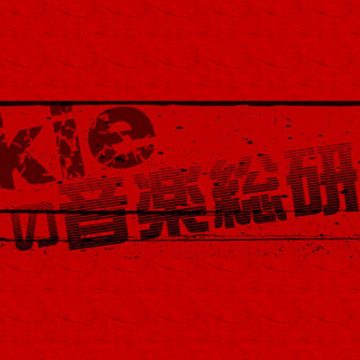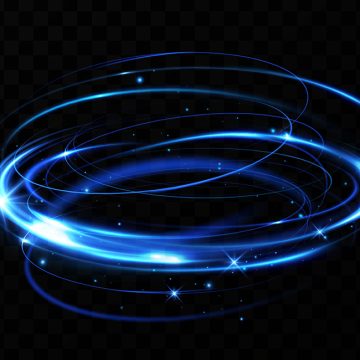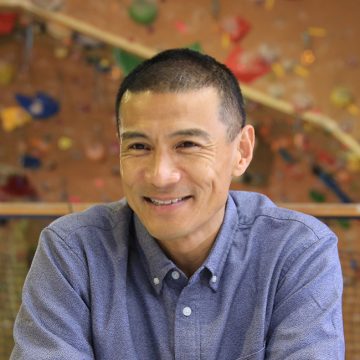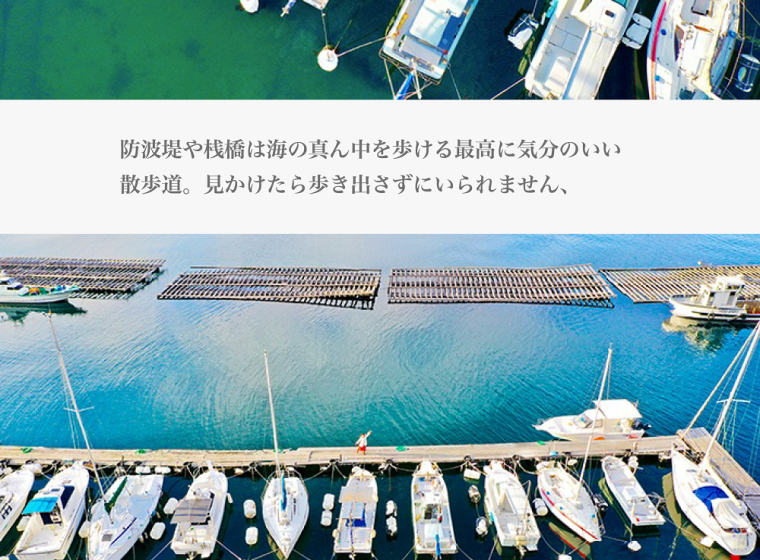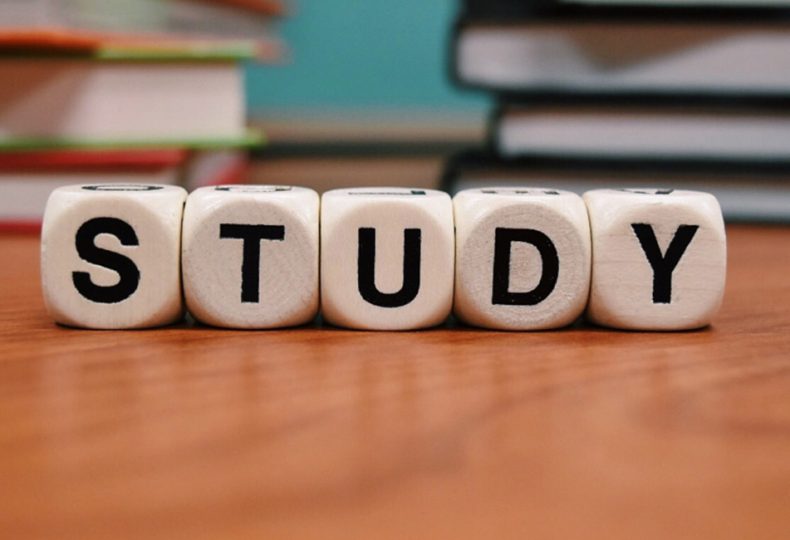
《外国語を身に着けたいあなたへ ~その1~》
日本では小学校高学年から英語の授業が導入され、ほぼすべての日本人が中高6年間ではかなりの単語数を覚え、文法や様々な言い回しを学んでいる。
だが一方で、「英語で思い通りコミュニケーションができる」日本人の割合は少ない。
AI技術の発展により、翻訳アプリも常に最良化アップデートされている今日この頃だが、私たちが外国語を身に着けたいという理由の一つには、「外国語も使ってコミュニケーションの幅を広げたい」という思いもあることを否めない。効果的に、また学びを難なく持続できる方法について、お伝えしていこう。
そもそも言語というものはコミュニケーションの一つのツールである。
「伝えたい」という思いがあることが、まず何より大切。
こどもが母語を吸収し言葉として使えるようになるまで、どのような仕組みになっているかをまず考えていきたい。
生まれてから、またお母さんのおなかにいるときからも、「耳」は多くの音をキャッチしている。そして、音を繰り返し聞くうちに、脳の中で「アルゴリズム」が出来上がってくる。
音というよりもむしろ同じ周波数のバイブレーションを一定量聞くと、それに対して脳が分類をしていく。
こうして私たちの脳に母語である日本語が組み込まれていく。
組み込まれた「日本語」の箱の中にさらに細かく「名詞」「動詞」「感情を表す装飾語」など分類がどんどんされていき、言葉として蓄積されていくのだ。
そのほかの器官の発達に伴い、複数器官での認識の発達がおきることで、自分で発する音の周波数も母語である日本語に寄っていき、「言葉」が出てくるようになる。
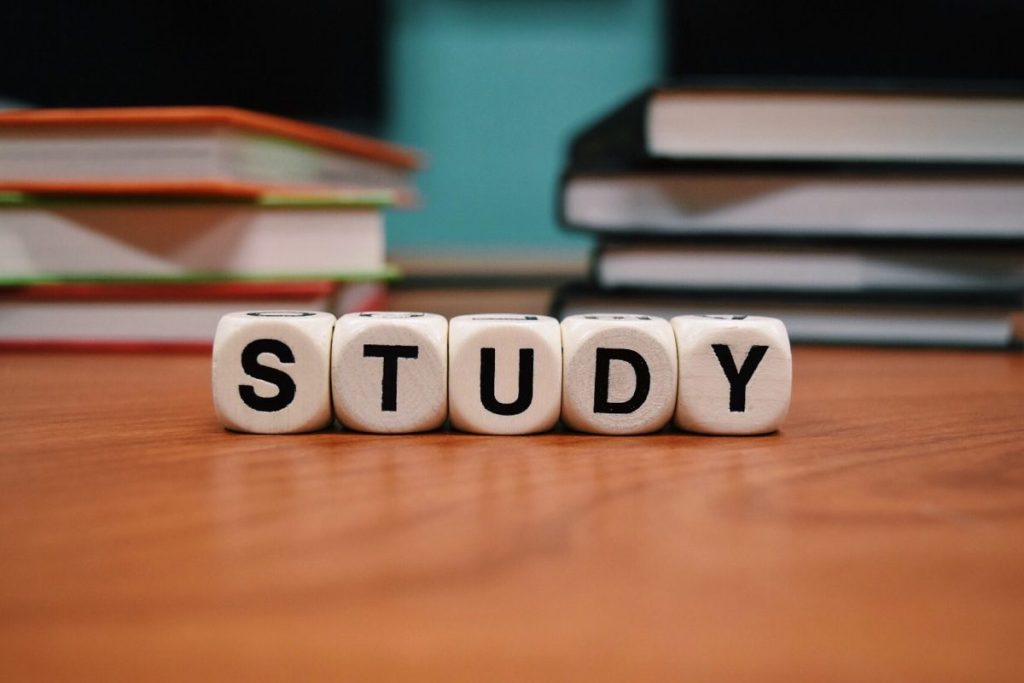
「言葉」は「意味」を持つことは聞こえてくる音、見えているモノ、その音の持っている性質(エネルギーや感情など)を伴い、そのデータがどんどん「日本語プログラム」の中に増えていく。そうやって私たちは言語を習得している。
コミュニケーションとしての言語を身に着ける際に、この母語の習得の流れをはめ込めばおのずと言語は身についていく。
筆者の場合も単身渡米した際にはほぼ全く話すことができなかった。
3ヶ月ほどほぼ日本語を耳にせず英語だけで生活していると、だんだんとアルゴリズムができてくる。加えて、中高で学んだ英単語や文法も手伝って、半年たつ頃には日常会話が難なく英語でできるようになり、1年たつ頃には言語を習得できていた。
もちろん、専門的な言葉や知らない言葉も数多くあるが、それは母語であっても変わりないこと。

この第2言語の回路が開くと、その後身に着ける第三言語第四言語のアルゴリズムができるまでのスピードが変わってくる。
これは先ほど触れた周波数の話に関わるのだが、言語はすべて異なる周波数を持っている。
母語とは違う周波数の第二言語を習得すると、キャッチできる周波数が増えるので、おのずとそのほかの似ている言語の習得が早くなると考えられる。
また、言語は文化からなっているものが多く、もともとの言語の派生文化が似ている場合は、文法などのつくりが似ている言語に関しては、なおさら理解が早いということもあるだろう。
これが、私たちが言語を習得するときに起こっている仕組みである。
ではつぎに、実際に身に着けるやり方をいくつかお伝えしていこう。
その2へ~